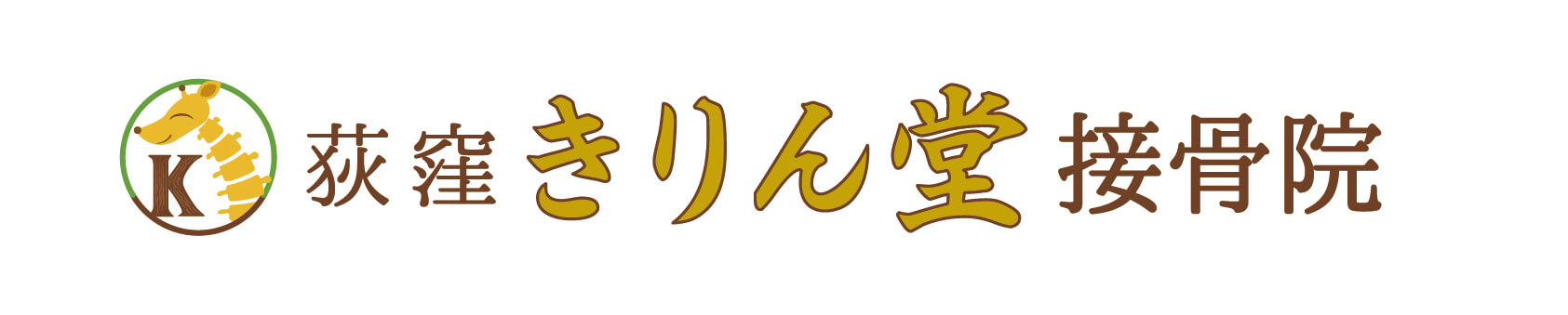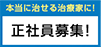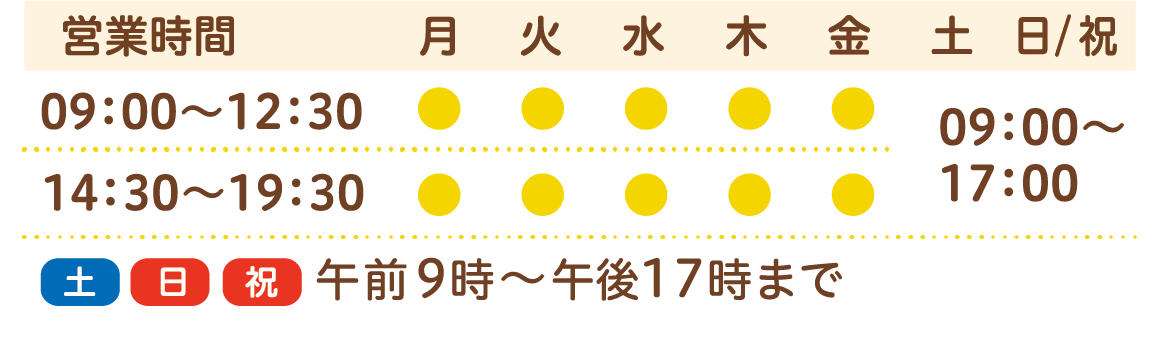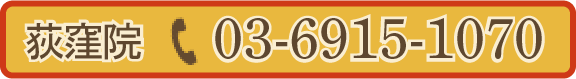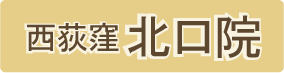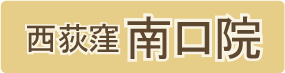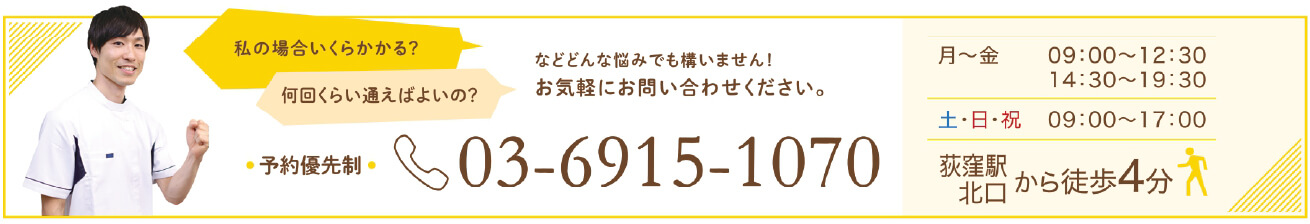今回は肩こりの悪循環についてお伝えしていきます!
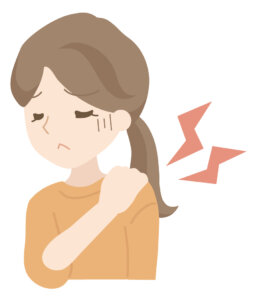
筋肉の長さのバランスが大事
深筋膜の下には、筋外膜によって束ねられた骨格筋があります。
みなさんもご存じの上腕二頭筋や腹直筋などです。
人体には約650個の筋があり、全部で体重の約40~50%を占めています。
筋肉は収縮と弛緩をすることで、姿勢や運動をコントロールしています。
筋肉にはほどよい長さが必要で、ほどよい長さにあれば柔軟性もあり、筋力も強く発揮できます。
正しい姿勢とは、筋肉がほどよい長さに保たれていて、効率よく筋力を発揮でき、かつ柔軟性も兼ね備えた状態なのです。
でも、不良姿勢などで、本来の正常の長さよりも伸ばされて長くなった状態にある筋肉は、力を発揮しづらくなり筋力が低下します。
逆に、短くなりすぎた筋は柔軟性がなくなり、こりも生じます。
つまり、筋肉の長さのバランスが崩れて、短い長さでいつも働いていなくてはならなくなった筋肉には「こり」が生じます。
悪い姿勢や間違った動きで、いつも頑張り続けなくてはいけなくなった筋肉も「こり」の原因です。

こった筋肉はどのような状態?
いわゆる「こり」は、一部の筋肉への過剰な持続的な収縮や疲労、長時間の悪い姿勢などによった、筋肉の血流が悪くなり、筋肉が硬くなり、痛みも引き起こした状態です。
症状としては、首、肩、肩甲骨、腕にかけての不快感や重圧だるさ、こり感などがあり、いつもでなくても痛みやしびれ感を感じることもあります。
「こり」は、長時間にわたって同じ筋肉に負荷が加わることで、筋が収縮し続けることで血管が圧縮されて血行不良に陥り、乳酸などの老廃物も滞ります。
血行不良による血流不足によって、血流内の酸素が少なくなります。
筋肉のエネルギー供給源となるアデノシン三リン酸(ATP)やアデノシンニリン酸(ADP)、クレアチンリン酸などが欠乏します。
すると、この状態を修復しようとして、さまざまな痛覚過敏物質が放出され、神経も刺激して痛みを起こします。
さらに、交感神経の活動まで高めることになり、局所の虚血状態も生じます。
つまり、筋肉に力を入れ続けていると、血流が悪くなり、酸素が運ばれなくなります。
筋肉の収縮をゆるめてリラックスさせるために必要なATPがますます欠乏し、筋肉は収縮しっぱなしになり、無意識のうちに「こり」や「痛み」が続くことになるのです。
血圧の人や高血圧が長い人も、血流が不足するので要注意ですね。
そして、「こり」は、その筋肉をおおっている筋膜のよじれも加速し、筋膜もよじれたままでほぐれなくなるのです。
筋膜と筋肉の両方が「こり」の原因として重なり合ってくるのです。
この状態は、筋・筋膜痛症候群とも言われています。
「こり」の悪循環をまとめると、、
筋肉の持続的緊張
→血行不良・酸素不良
→乳酸などの老廃物の滞り
→筋肉のエネルギー供給源の欠乏
→痛覚過敏物質の放出
→神経も刺激して痛みも増加
→交感神経刺激でさらに虚血、酸素不足
→筋にリラックスに必要なATP欠乏
→無意識でも筋肉収縮持続
→「こり」の完成
→最初の筋肉の持続的緊張に戻る

悪循環にはまると怖い肩こりですが、杉並区の荻窪駅から徒歩3分にある荻窪きりん堂接骨院では、悪循環を断ち切るための施術やホームケアの指導を行っております。

肩こりでお困りの方はお気軽にご相談ください。
参考文献: 肩こりにさよなら! あきらめていたすべての人へ
著書 竹井 仁